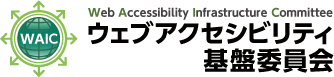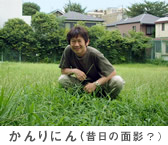ウェブアクセシビリテとは、ウェブページにある情報や機能の利用しやすさを意味します。しかし、もっと狭義には、総務省が推進している目の不自由な人など障害者にも使いやすいWEBのあり方をさしています。総務省が旗振り役になっているため、現在、ほとんどの官庁ではその規定を守った、目の不自由な人など障害者にも使いやすいWEBがつくられるようになっています。
その品質を確保する際の拠り所となるガイドラインは、ウェブ技術の標準化団体であるW3Cの定めたものから企業が独自に制定するものまで多種多様ですが、JIS規格として制定されたのが規格番号JIS X 8341-3、規格名称「高齢者・障害者等配慮設計指針 ?情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ」です。
2004年6月に制定されたJIS X 8341-3は、2010年8月、ウェブアクセシビリティの事実上の国際標準であるW3Cの発行したWeb Content Accessibility Guidelines(WCAG)2.0と協調するよう改正されました。これにより、WCAG 2.0、ISO/IEC 40500:2012、JIS X 8341-3:2016の3つが全て技術的に同じ内容になり、W3Cの勧告、国際規格のISO、国内規格のJISが統一されることになります。
私見では、JISがそんなことを決めるのには疑問がある。よって、私がフリーでWEB制作をしている期間において、JISの規格にはとくに興味はなく、それに準拠しようという気もなかった。おそらく、ほとんどのWEBデザイナーはそうだろう。しかし、派遣で仕事をするようになり、その派遣先がたまたま官庁系であったので、このJISの規格にもとづいたウェブアクセシビリティを意識した制作をおこなわざるをえなくなった。
これは、派遣という外の海へ出たことで、たまたま経験できたことである。一人でやっていたら、決して経験できなかった世界だ。それは、よかったと思う。とりあえず、ウェブアクセシビリティの知識も得られ、実践もできるようになり、また視野も広がったと思われる。めでたしめでたし。