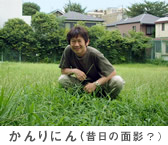アクセシビリティとは、使いやすさや利用しやすさをあらわすWEBの用語として使われる。技術に依存せずさまざまな情報端末やソフトウェアから利用できることをさす。しかし、実際にホームページについて、この言葉が用いられるとき、日本では総務省が打ち出したものとして、つまり、もう少し狭く、障害のある人が、コンピュータの画面を読み上げるスクリーンリーダーなどの技術を利用して利用しやすいウェブのサービスであるといった意味で使われている。
総務省は、JIS規格の適用を指示している。2016年3月22日に改正された日本工業規格JIS X 8341-3:2016 「高齢者・障害者等配慮設計指針?情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス?第3部:ウェブコンテンツ」に基づいて、高齢者や障害者を含めた誰もが利用しやすい情報の提供を目指している。この規定にもとづき、ホームページをつくることが求められている。

さて、前置きはこれぐらいにして、私は派遣先で2年連続、アクセシビリティチェックにもとづくHTMLの修正をおこなった。チェックは専門の業者さんに依頼してやってもらい、その報告書を見て、HTMLを修正するのである。2年連続でやったので、だいたいどういうところが問題で、どのように修正すべきかがだいたい把握できた。もっとも多いのは、リストで記述すべきところをリストで記述するということである。次は、ALTを詳しく入れることだろう。その次は、画像の文字においてコントラストを高くすることだ。
チェックされたとおりに修正するのだが、チェックは厳しい。細かく見ており、重箱のスミをつくように指摘されている。もちろん、それはありがたいことだ。しかし、問題があると思うのは、画像の関係でデザインに関わってくることだ。画像で用いる文字は、かなり濃い色でなければならない。パステルの文字などもってのほかだ。そうすると、デザインの許容範囲がかなり狭められ、不自由になってしまう。
上の画像で黄色い文字「ACCESSIBILITY」を入れたが、このコントラストでは完全にアウトだ。
いずれにしても、アクセシビリティのアドバイス、改善の依頼も受けられますので、よろしく。